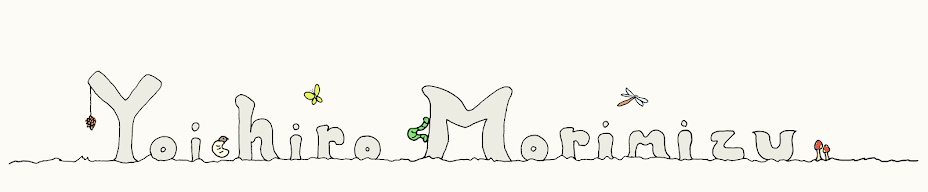昨秋に自宅前で保護した、人慣れした茶トラのオスで、最後まで威嚇の声を上げることのない、おだやかな性格の持ち主だった。
残念ながら猫白血病ウイルスのキャリアで、重い腎臓病を患っていたが、動きは俊敏、元気そのもので、朝夕の食事もぺろりと平らげ、「寝子」の名に恥じない、時間からほどかれた生き方を見せてくれていた。
新鮮な水と、良質な餌と、カイロの敷かれたあたたかな寝床。
万が一のために怪我用のペット保険に加入したが、私はあくまで彼の生活をサポートするだけで、必要以上の介入はせず、気の合う森の一員としてともに暮らしていた。
いろいろ手を尽くしたが元の飼い主は見つからず、残酷な考え方になってしまうが、ポッケの病状を知ったうえで、森に捨てられた可能性もそこにはあった。今後の面倒を見切れないから、どうかうまく生きてくれと。
病気については調べれば調べるほど、行く手にほの暗い雲が垂れ込めており、目の前のポッケとのギャップが大きいだけに、心にこたえた。猫には珍しく、お腹をなでられるのが大好きで、甘えてくればできるだけ付き合ってあげた。のどの奥の小さな雷鳴が遠のいてしまうまで。
今年の千葉は暖冬で、12月の初めに少し寒い日が、そして1月の終わりに、小雨をともなって本格的な冬が訪れ、もしかするとその冷たい雨が、何らかの影響をもたらしたのかもしれない。
ある朝、左目をしょぼつかせていることに気づき、それにともなって食欲が目に見えて落ちた。野鳥や野ねずみを捕らえたり、どこか別の家で餌をもらっているのならまだ安心だが、お腹にふれても満腹の横張りはなかった。口から食べ物の匂いもなく、首輪に書かれたこちらの電話番号に「うちでも与えてますよ」という報告もなかった。
念のために、首輪につけるタイプの小さなGPSを購入し、負担にならないよう二日間だけ使用してみた。すると一晩で3キロ近くあちこち散歩しており、森から離れた海岸線まで遠出していることが明らかになったが、かといって安心にはつながらなかった。世間のすべての人が猫好きであるとはかぎらず、実際、無知による弊害として、猫にとって有害な、サザエの肝を吐き戻したことが過去にあった。
ほどなく、腫れこそないが、結膜炎らしき赤みがまぶたに認められ、自然治癒を待たずに病院に行くべきか思案していたところに、左の後ろ足の負傷という不幸が重なった。保護してすぐのころ、左前足を捻挫したらしく、それが一週間ほどで回復したのを見ていたのだが、今回にかぎって、横になるさいに痛がる鳴き声を上げ、すでに食欲も、食べない日があったり、食べても5分の1程度であったり、もう迷っている時間はなかった。
診察の結果、さいわい骨折はなかったが、グラフからはみ出るほど腎臓の数値が悪く、二日間、点滴の食事と抗炎症薬で様子を見ることになった。その入院が正解であったのか、いまだわからない。残念ながら数値は下がらず、レントゲンでも約2倍の大きさに肥大した腎臓の影を見せられ、今後の選択肢を提示された。
私は迷うことなく、連れ帰ることにした。なれない環境と、治療によるストレスがあったのだろう、すでに自力では尿を排出できず(あるいはかたくなに排出せず)、下手をすると尿毒症にまで発展してしまう。一刻でも早く、森に連れて帰るべきだと考えた。獣医もそれを承諾した。
さいわい、自宅に戻ってすぐ、安心したのか草地での排尿があり、水にも口をつけたが、そこからは苦しい日々が待っていた。いつものドライフードを与えてみたが、一切口をつけず、温めたり、柔らかくしたり、いろいろ試してみたが、ドロドロの粥状にしてようやく、シリンジ(注射器)で口に流し込むのが精一杯だった。ちゅーるなどの食べやすいおやつも何種類か用意したが、どれも顔をそむけるばかりだった。
日を追うごとに体重が減り、出かける範囲が庭先だけになった。それでもなんとか流動食を食べさせ、命をつないでいたが、悲しいことに、あれだけ食べることが楽しみだったその日常が、すべて裏返ってしまった。口をあけさせて、シリンジで流し込むたびに、ポッケは衰弱した体で、どうにか前足を上げ、上体をひねって抵抗しようとする。食事のたびに、残り少ない体力を消耗する。
もちろん、ふたたび病院に連れて行き、チューブを口に突っ込んで栄養を流し込んだり、前足の出血をともないながら点滴を打つこともできただろう。しかし私は、その選択肢を選ばなかった。たとえ一時的に回復できたとしても、奥で待ち受ける白血病と腎臓病にともなう症状が消えるわけではない。衰弱こそしているが、あきらかな苦しみも、目に見える腫瘍もないいまの状態を、チューブや点滴でいたずらに引き延ばし、生き長らえさせるのは、森に暮らす半野生の、生き物としての尊厳を奪うように思えたのだった。
すでに毛づくろいが難しく、水を飲む量が減った。5歩歩くのもやっとで、もしハクビシンなどの野生動物に襲われても、到底逃げ切れるはずもなかった。しかしたとえそのような悲しい結末が待っていようとも、そこに命の無駄はない。森を循環する流れの一部として、ポッケの体が美しく取り込まれるだけだ。
私はポッケをあぐらの中に抱き、話して聞かせた。もう苦しい思いをさせない、無理矢理食べさせない、だから抱っこしても、もう逃げなくてもいいと。ポッケは目を見ひらいて、じっと私を見ていた。私はゆっくりとまばたきを返し、彼への想いを伝えたが、それが届いたのかはさだかでない。
決意から息を引き取るまでの2日間、千葉は小春日和だった。ポッケは一日中、私の目の届く範囲、庭先の、スギナが芽吹いたばかりの草地で、じっとふせをし、ときどき体の向きを変えて、お日様のあたる場所をいれかえ、のんびり一日を過ごした。
腎臓ケアのドライフードと、スープ状の餌と、新鮮な水を用意したが、どれも口をつけなかった。それでも夜になると、玄関先のひさしの下に作られた、特注の小屋の中に時間をかけてもぐり込み、私はボサボサになってしまったその毛並みを、やさしくくしでといた。いくらなでても、話しかけても、ポッケの雷鳴は聞こえなかった。
2月16日の朝、ひさしぶりに千葉に冷たい雨が降り、私はポッケの旅立ちを知った。
濡れた庭にいつもの姿はなく、小屋のふたをあけると、ポッケは毛布のなかでじっと横たわっていた。その瞳は見ひらかれ、呼吸を示す膨らみも消え失せていたが、さわるとまだ温かく、抱き上げるといつものポッケの柔らかさがそこに生きていた。
ポッケは愛玩動物ではなく、森の住人だった。だから還る場所も決まっていた。
私はタオルを敷いた段ボール箱に、ポッケの体を移し、そこに大好物だった餌と、私が焼いた素焼きの、アケビほどの大きさの土のひとがたを納めた。
小雨の降りしきるなか、家の裏の高台に向かい、そこにシャベルで深い穴を掘った。野生動物に掘り返されることのないよう、1時間かけて、深い深い穴を掘った。そしてポッケに最後の言葉をかけ、穴の底に段ボール箱を寝かせて、そこに少しずつ土をかけた。
不思議と涙は出なかった。別れの悲しみはなかった。顔の前で手を合わせると、ほのかにポッケの匂いがして、つかず離れず森の小道を散策した、彼との日々が思い出された。りりしい背中と迷いのない足取りが思い出された。
また会おう、ポッケ。楽しい日々だったよ。
 |
| 首輪とくし。手元に残したもう一つのひとがた。 |